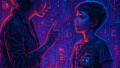『問いかけの作法 チームの魅力と才能を引き出す技術』 要約
本書は、沈黙や受動的な態度に陥りがちなチームを活性化させるために、「問いかけ」の質を変えることで成果を引き出す技術を解説している。従来の指示や要求ではなく、工夫された問いかけによって、メンバーが自発的に意見やアイデアを出せるように導くことを目的とする。
著者が定義する本質は、「問いかけはチームの潜在能力を引き出す鍵である」ということ。問いかけは単なる質問ではなく、メンバーの個性を尊重し、創造性を刺激し、場の雰囲気を変える力を持つとされる。
特徴:
- 「孤軍奮闘の悪循環」を断ち切り、チームに主体性を取り戻す
- 仮定法・パラフレイズ・足場かけといった具体的な問いかけ技術を解説
- ファクトリー型とワークショップ型の違いを踏まえた現代的なチーム論
- 問いかけを「スキル」として誰でも習得可能にするモデルを提示
- 教育・ビジネス・日常会話にも応用できる実践的アプローチ
こんな人に読んでほしい
- ミーティングで沈黙が続き、チームが停滞しているリーダー
- 部下や同僚から主体的な意見を引き出したいマネージャー
- 組織の創造性を高めたい経営者・プロジェクトリーダー
- 子どもや学生の発想を伸ばしたい教育関係者
- 日常の人間関係で建設的な会話を育てたい人
本書の重要な点
- 問いかけは「指示」ではなく「才能を引き出す技術」である
- 質問の仕方を工夫することで、沈黙は議論へ、受動は主体性へ変わる
- チームの停滞は個人の問題ではなく、問いかけの設計の問題
- ワークショップ型組織では「こだわり」を引き出す問いが成果を左右する
- 良い問いかけは、相手の意見を尊重し、楽しさを伴いながら答えやすくする
この本でどんな変化が起きるのか
- Before: ミーティングが沈黙のまま終わる / メンバーが意見を言わない / リーダーが孤軍奮闘
- After: メンバーが自然に発言する / アイデアが次々に出る / チームに活気と信頼感が戻る
- Before: 指示と要求が中心で、受動的な態度が広がる
- After: 創造的なやり取りが増え、個々のこだわりが成果につながる
この本を読んだら今日からできること
- 「意見は?」ではなく「この案、1つだけ変えるなら?」と具体的に問いかける
- アイデアを引き出すときは「仮に自分が顧客だったら?」と仮定法を使う
- 発言しやすくするために「今浮かんだことを1つだけ教えて」とハードルを下げる
まとめ
本質は「問いかけがチームの未来を変える力になる」という点にある。チームに沈黙や停滞を感じている人は、まず自分の問いかけを変えることから始めよう。それが仲間の才能を引き出し、チームの成果を最大化する第一歩となる。